アイシングとは、怪我や炎症を起こした部位に氷などで冷やすことで、痛みや腫れを抑える処置のことです。スポーツや日常生活でよく用いられる方法ですが、実はアイシングにはメリットとデメリットがあります。この記事では、アイシングの効果や注意点について解説します。

アイシングはどんな時にするの?
野球選手の投球後のアイシングに関してはよく見られている方も多いかと思います。以前は当たり前のように投球後はアイシングを実施していましたが、現在は様々な意見があり、アイシングをせずに軽運動でコンディションを行う選手も多くなってきました。
一般的には炎症所見が見られる際にRICE処置という応急処置としてアイシングを実施していきます。
それでは実施にどんな効果や目的があり、実施時間など方法をご紹介していきます!
アイシングの効果とは
アイシングの効果は大きく3つに分けられます
アイシングの効果は主に以下の3つに分けられます。
- 痛みの緩和
- 炎症の抑制
- 出血の防止
痛みの緩和は、冷却によって神経伝達速度が低下し、痛みを感じる信号が遅れることで起こります。
また、冷却によって血管が収縮し、血流が減少することで、一時的に幹部とその周囲の細胞の代謝レベルが下がります。これによって、炎症の進行が抑制されます。さらに、血管の収縮によって、損傷部位からの出血も減少します。これによって、損傷部位の腫れや内出血が防止されます。
炎症は、組織修復に不可欠な反応でありますが、炎症が大きくなると二次的低酸素症が誘発され、周囲の健康な組織にも障害が広がります。
アイシングの方法
アイシングの実施時間
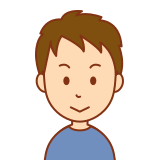
アイシングはどれくらいしたらいいのだろう?
アイシングは一回につき10分〜20分を目安に行います。しかし、これは部位によって異なります。 例えば、指と大腿部では深部まで冷却するまでの時間は大きく異なります。
1.アイシング開始から数分間は強い冷却感
この強い冷却感によりアイシングに慣れていない人はすぐに外してしまう人が多いですが徐々に感覚が麻痺してきて慣れてきます。
2.10分〜12分後に寒冷起因の血管拡張により暖かい感覚になる
3.その後3分〜5分で血管収縮期に入ります
4.深部の冷却により感覚鈍麻が生じる
触られても感覚が鈍くなりますが、そこまで経過すると、深部冷却効果が得られます。
この深部冷却までおよそ10分〜20分となります。
アイシングの間隔
次にアイシングの間隔は1〜2時間に1回の間欠的に行うことが望ましいです。
そして、この間欠的なアイシングを急性期の炎症期間である24〜72時間行うことが望ましいです。
怪我の重症度によって炎症の反応は違うため、重症度に合わせて間欠的なアイシングを継続して行いましょう。
重症度の判別は専門医の受診を勧めます。
冷却媒体
冷却媒体は氷が優れています
氷は0℃を基点に個体から液体に変化します。この時要するエネルギーを融解熱と言います。
氷が液体へ変化する時は約80cal/gの融解熱を要します。つまり、氷を当てている部分はその分だけ冷却効果を得ている(熱を奪う)ことになります。
対して保冷剤などを冷凍庫でカチカチに固まってしまった場合は冷却効果が下がるとともに凍傷の危険も高くなるので注意が必要です。
どうしても氷が準備できない時は、保冷剤でも良いかと思いますが、タオルで包んだり、冷却時間に注意しながら使用をしてください。
Ship-fitness
- 基本的にアイシングは氷を勧めますが、氷の中にも2つ種類があります。
アイシングの効果を得るには冷却媒体が皮膚表面に密着していることが大切です。
板状の面を作るのに適したキューブアイス
大腿部など面積の大きい部位を冷やすのに最適です。

凹凸のある場所に形を合わせやすいクラッシュアイス
足関節など骨が隆起している部位に最適です

アイシングを作成する際は、袋に氷を入れ、空気を抜きましょう。空気が入ってしまうと、患部と氷の間に空気の層ができて冷却効果を十分に発揮できなくなりますので注意してください。
アイシングの注意点とは
アイシングには上記のような効果がありますが、適切に行わないと逆効果になる場合もあります。アイシングには以下のような注意点があります。
アイシングの時間と頻度
アイシングの時間と頻度は、損傷の程度や部位によって異なりますが、一般的には10〜20分程度を1回とし、2〜3時間おきに行うことが推奨されます。長時間や頻繁に行うと、冷えすぎて皮膚や神経に障害を起こしたり、血流が悪くなって筋肉や組織の回復が遅れたりする恐れがあります。
アイシングの対象
アイシングの対象は、主に急性期(損傷後24〜48時間以内)の損傷です。急性期では痛みや腫れが強く出るため、アイシングでそれらを抑えることができます。しかし、慢性期(損傷後数日以上経過した)の損傷では、アイシングではなく温める方が効果的です。温めることで血流が増えて栄養や酸素が供給されやすくなり、筋肉や組織の回復を促進します。
表在覚の障害
表在覚の障害は特に温痛覚が鈍磨している方(温度や痛みが感じにくい)は凍傷のリスクとなるため、冷却時間や冷却媒体の温度に特に注意が必要です。
アイシングの適応にならない人
冷却刺激を加えることによって、アレルギー反応や循環障害を起こす人がいます。このような人はアイシングの適応になりません。例えば、冷却刺激によって湿疹(寒冷蕁麻疹)が出る人、冷却刺激によって末梢の血流が低下し、チアノーゼ状態(レイノー現象)などがあります。特に初めてアイシングをする人はこれら症状を気にかけながら行ってください。
まとめ
アイシングは、怪我や炎症を起こした部位に氷などで冷やすことで、痛みや腫れを抑える効果があります。しかし、適切に行わないと逆効果になる場合もあります。アイシングの時間と頻度、方法、対象に注意して行いましょう。アイシングは急性期の損傷に有効ですが、慢性期の損傷には温める方が良いです。損傷の程度や部位に応じて、アイシングと温めるを使い分けましょう。



